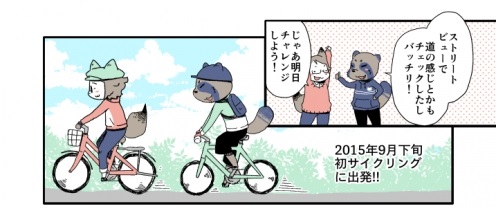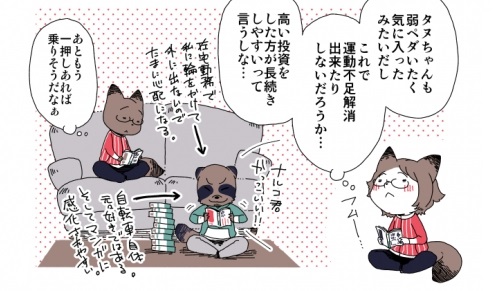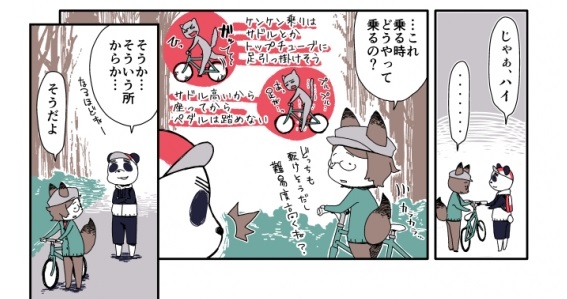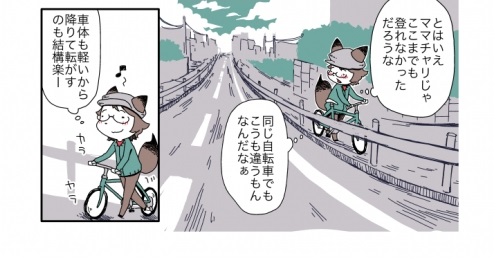街乗り用スポーツ自転車で有名なRITEWAYのグラベルロード「SONOMA ADVENTURE」。2019年モデルはがらっと変わったので解説する。

ライトウェイのスポーツサイクルは、街乗りやサイクリングを中心に楽しむ人向けの自転車。グラベルロードのSONOMA ADVENTUREもスマートフォンホルダーやセンタースタンド、マシュマロサドルが付いており、他のグラベルロードよりも、街乗りやサイクリングに適した自転車となっている。
ただ、従来のSONOMA ADENTUREとの違いは、近年流行しているグラベルロードのデザインを採用していること。クロモリ製のフレームには13か所、クロモリ製フロントフォークには6か所のボトルケージマウント用ネジ穴を装備している。
そのためボトルケージなら最大7個を取り付け可能とのこと。流行のボトルケージ台座に装着するタイプのキャリアを装着して、ボトルケージが装着できなくなる問題は無いだろう。
650Bホイールと700Cホイールの2種類を選ぶことができるSONOMA ADENTURE

SONOMA ADVENTUREの一番の特徴は、650Bホイールと700Cホイールの2種類を選ぶことができること。
650Bホイール仕様は、一般的なクロスバイクよりもタイヤが太く安定性やダートや段差に強いグラベルロード向けタイヤ(KENDA・FLINTRIDGE 650B×45C)を装備。700Cホイール仕様は、シティサイクルと同じくらいのタイヤ幅で舗装路用のスリックタイヤ(RITEWAY アーバンフルスリックタイヤ 700×35C)が付いてくる。
多くのグラベルロードバイクでは700Cホイールと650Bホイールの2つのホイールに対応しているモデルが増えているが、SONOMA ADVENTUREのように700Cホイールと650Bホイールから選べるのは珍しい。
買う時は650B仕様か700C仕様のどちらを買うか迷うだろう。筆者の考えは、スピードよりも道を気にしないで走りたい人には650B仕様。舗装路を快適に走りたいのなら700C仕様を選ぶだろう。
因みに650Bホイール、700Cホイールともオプションで購入できる。また、ハブの規格は汎用性が高いクイック仕様を採用しているため、ホイール交換も容易なので、気軽に特徴を変えることができる。
欠点は車体重量が13kgと重く、車体サイズが2種類と少ないこと。しかし、価格が89,800円(税抜)なのを考えると、ドロップハンドルタイプのツーリング用自転車と考えると悪くないと思う。
10万円以下のロードバイク/グラベルロードまとめ https://t.co/reLoMX74mq #自転車 @CycloriderJapanさんから
— CycloRider (@CycloriderJapan) December 12, 2019