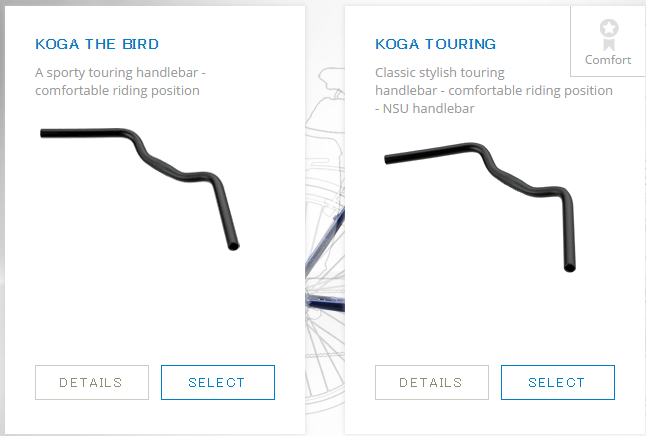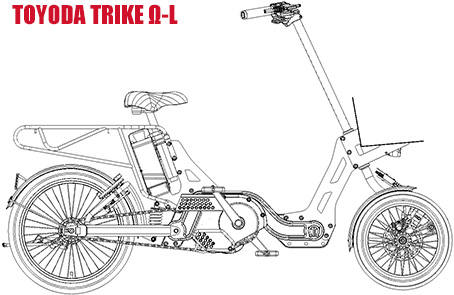近年のソフトやネットサービスでは定額制で使い放題を売りにしたり、利用権を借りて利用した期間に応じて料金を払うサービスが多い。これは、一般的にサブスクリプション方式と呼ばれる方法で、イニシャルコストが不要になる利点がある一方、そのサービスを長期間使用する場合、料金をずっと払わないといけないという欠点がある。サブスクリプション方式ビジネスモデルで成功した事例といえば、Adobe Creative CloudやAmazon プライムビデオ・プライムミュージックが挙げられる。
サブスクリプション方式ビジネスモデルはネットやソフト関連のサービスだけでなく、自転車業界でもこのビジネスモデルを採用したサービスがある。スニークルロングタイムシェアは、月額3,480~5,980円でスポーツサイクルが乗り放題になるサービスで、サービス1台目の自転車は180日、2台目からは90日間乗車することで乗り換えを行うことができるサービスだ。
http://www.sneecle.me/
似たようなサービスを挙げるとすれば、自動車の乗り放題サービス「NOREL」を思い出す人もいると思う。スニークルロングタイムシェアはNORELの自転車版だと思っていいだろう。
https://norel.jp
月額3,480~5,980円で自転車乗り放題サービス「スニークルロングタイムシェア」はお得なのだろうか?今回はスニークルロングタイムシェアがお得なのか考えてみた。
スニークルロングタイムシェアで借りることができる自転車はどういう物なのか
スニークルロングタイムシェアで借りることができる自転車は、2017年11月22日現時点では、ロードバイク、ピストバイク、折りたたみ自転車、マウンテンバイクと様々なスポーツサイクルがレンタルできるようだ。
ここで気になるのがマウンテンバイク。借りることができるマウンテンバイクは下り坂を高速で走るモデルやジャンプ系のモデルがある。レンタル用の自転車でマウンテンバイクコースやダートジャンプコースを走るには高い確率で壊れる可能性があるため、このような自転車を借りても、しかるべき場所で走れるのは難しい。
また、スニークルロングタイムシェアで採用されている自転車のは中古車。納車までに清掃、整備を行い、使用できる状態で渡すとのことだ。
スニークルロングタイムシェアの契約条件
スニークルロングタイムシェアの契約条件は2017年11月22日現在では、以下の通り。
- 18歳以上。
- 敷地内に屋根付の駐車場又は室内での保管が可能な方。
- 顔写真入り身分証明書がある方。(写真がない場合は2つ以上の書類が必要(住民票と保険証、等))
- 日本人の方、もしくはビザが2年以上、永住権のある方のみ。
また、賠償責任保険は交通事故時の賠償責任保険がユーザーが独自で加入する必要がある。
解約金はいくらかかるか?
スニークルロングタイムシェアの契約期間は2年間(更新は自動更新)。また途中解約の場合は違約金が発生する。解約(更新せず)の連絡は1か月前から可能、原則解約日(契約満了日)当日に自転車を返却することができるとのこと。
http://www.sneecle.me/faq/
スニークルロングタイムシェアは途中解約の場合、違約金として30,000円がかかる問題がある。
スニークルロングタイムシェアは、あくまで乗ることができるだけで所有できない。自転車を趣味にすると自転車は体の一部になるため、スニークルロングタイムシェアを使う場合、所詮試し乗り程度しか扱うことしかできないが、2年間も契約するのは長すぎる。違約金を5,000円~10,000円と安くするか、6ヶ月程度の自動更新がいいところだろう。
スニークルロングタイムシェアは本当にお得か?
スニークルロングタイムシェアで欠点となるのが、乗ることしかできないことと違約金が高いことだろう。特に違約金は高く、違約金を我慢して使うにしても3980円の自転車を使うと二年で10万円近く。5980円の自転車だと15万円近くかかる。違約金を5,000円~10,000円と安くするか、6ヶ月程度の自動更新にすれば面白いと思うが、違約金が高すぎるので躊躇してしまうのが本音だ。